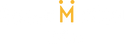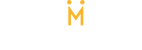第14回目の授業には、人類学者であり山梨県立大学特任教授、さらに合同会社メッシュワークの共同創設者を担われている比嘉夏子先生をお迎えし、「人類学的に『みる』ということ」をテーマに講演とワークショップを行いました。
「見る」とは何か
講義ではまず、人類学における「みる」ということについて、その重要性についてお話しいただきました。 情報・データが溢れている現代社会において、それらを解釈して洞察する力や、身体的な直接体験が軽視されている現状が指摘されました。その上で、人類学とは「直接体験を通して何かを考えることを大切にする学問である」とお話しされていました
。例えば、会議の場での発言には注目するが、「どのようなペンを使っているのか」「どの席に座っているのか」といった情報はなかなか注目されません。
また、比嘉先生のトンガでのフィールドワークをはじめとした観察の経験を踏まえ、「メッシュワーク」という概念をご紹介いただきました。 「メッシュワーク」は「ネットワーク」と区別して使用されますが、輸送のように効率的に目的地へ向かうのが「ネットワーク」 「メッシュワーク」的なアプローチを行うことで、効率を優先した見方からは見えなかった世界を見ることができると語られていました。
関わりながら「みる」、みたものを「言語化」する
さらに、観察の手法を使って、観察対象に様々な段階で関わりながら観察することについてもご紹介いただきました。
加えて、先生は「みる」だけでなく、見たことを言語化することの重要性についても話しました。 ここでいう言語化とは、「見たことを思い切って書く」ということです
。を事前準備していると、その枠の中でしか答えが得られず、外部に広がる多様な可能性を間違えてしまう。 観察を行う時は、まずはぼんやりと全体を眺め、見えてきた事実を丁寧に理解します。
観察のワーク:動画をみてみる
後半は、動画をじっくり観察ワークを行いました。受講生はそれぞれを見て何を考えたか映像を書き、その後共有とディスカッションを行いました。ディスカッションを通して、同じ映像を見ても、それぞれの関心によって着目点が大きく異なることが分かりました服装に注目している人や、建築や交通システムを見ている人など、観察の対象は多岐にわたりました。受講生からは、音声などの視覚以外の感覚に注意が向きにくいという声もありました。また、観察したものから、季節や時間帯などの推測を行う人もたくさんいました。
このワークを通し、書き出せる要素は無限に存在し、その人の興味や背景によって見え方が変化することを認識しました。 実際のフィールドワークの現場では、音やにおいなど視覚以外の感覚を使って観察することが重要です。
今回の講義とワークショップ、「観察」とは静か対象を客観的に記録することではない、対象と関わりながら自分自身の認識や視点も含めて観察することだと学び。その過程で対象への認識が変わることこそが最大の目的であると比較嘉先生が話されていたことが強い印象に残りました。

これは、ストリート医療が求める「病を診ずして、人をみよ」というコンセプトの実践そのものであると感じました。対象を「みる」ことを育てみ、その過程で自らの見方もまた更新されていくという姿勢は、取り組む覚悟が今後の学びや実践において大切にし、重視してほしいと思います。