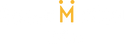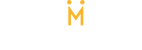2025年8月9日、第6期第13回目の授業には、病院マーケティングサミットJapan代表理事の竹田陽介先生をお招きし、「人と地域の未来を育む共創病院の作り方」というテーマで講義とワークショップを行いました。病院マーケティングサミットJapanの掲げる「すこやかな暮らしの共創」というコンセプトには、身体的な健康にとどまらず、ウェルビーイングの向上という意味も込められています。
ケーススタディ「未来へつながる地域づくり」
竹田先生は、病院を単なる「治療行為を行う場」としてだけでなく、「人々の暮らしや地域の未来を共に育んでいく拠点」として位置づける重要性を強調されていました。講義では、「すこやかな暮らしの共創」をめざし、地域や社会に病院が貢献してきた事例をご紹介いただきました。

社会福祉法人として「弱者救済」を理念とする済生会小樽病院では、「健康づくり」ではなく「くらしたい共創」というコンセプトを掲げ、病院を地域のハブとして町づくりを行っています。その一環として、地域住民が集まり、多様な交流や文化活動を行う「小樽くらしたい共生フェス」など、さまざまなイベントが開催されています。公共性が高く、人々のインフラでもある病院を拠点に町づくりを行うという観点は、とても理にかなっていると強く感じました。さらに、町民が健康なうちから病院とつながることで、町民と医療従事者の双方にメリットが生まれると理解しました。特にストリートメディカルラボで目指している「病を診ずして、人をみよ」が実践しやすい環境が整うのではないかと思います。
そのほかにも、高齢者が学びや交流を楽しめる「シニア大学」や、ハンディキャップのある方々が製造に携わる「フローズンとろみ日本酒」の事例も取り上げられました。この日本酒は、特定の人のために作られたものが結果的に誰にとっても価値ある商品となる「インクルーシブデザイン」の理念を体現しています。さらに、若者が自由に発想し行動できる環境を整えることが、地域資源や新たな産業の創出につながるという実例もご紹介いただきました。竹田先生は、医療や福祉、介護の領域に多様な老若男女が関わることで新しい価値が生まれ、地域全体の未来を形づくることができるとお話しされていました。

グループワーク「病気じゃなくても行きたくなる病院デザイン」
後半のワークショップでは、「病気じゃなくても行きたくなる病院デザイン」をチームで考えました。参加者は、病院をより魅力的で身近な場所にするためのアイデアを検討しました。コンテスト形式で行われ、全6チームのうち優れたアイデアを提案したチームには、竹田先生賞、沼田理事長賞、受講生の投票によって決まる受講生賞の3つの賞が贈られました。
陶芸やものづくりなどができる工房やジム、脱毛サロンといった定期的に通える場を病院に併設するアイデア、気軽に悩みを打ち明けられるバーやスナック、インドネシアのジャムウに着想を得て悩みに応じた食事や飲み物を提供するサービスのアイデアなどが挙げられました。さらに、病院という場所を活用したイベントを開催するという案も多く出されました。
コンテストの結果、竹田先生賞では「時間の経過による変化が感じられ、関わる人が多い」という点が評価され、沼田理事長賞では「大きなテーマが設定され、医療従事者と地域の人が交流できるアイデア」が評価されました

今回の講義とワークショップを通じて、病院が地域において果たす役割は医療提供にとどまらないことを改めて実感しました。多様性が謳われるこの時代において、「究極の多様性は、医療・福祉・介護の現場にある」とのお話が強く心に残りました。最も多様な人と接しているこれらの現場こそが、まさに多様性の最先端の場所であると改めて思いました。患者さんの病気だけでなく、生活や社会全体に目を向ける取り組みは、ストリートメディカルとも親和性があると感じました。