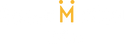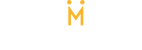2025年7月26日、第6期第12回目の授業には、公共空間のデザインを手がける飯石藍先生をお招きし、「私たちが育むパブリック」というテーマで講義とワークショップを行いました。
公共空間をどうやって「みんなのもの」にできるか?
講義の冒頭では、飯石先生がこれまで手がけたプロジェクトの事例から「公共のあり方」についてご紹介いただきました。最近では財政のひっ迫や人口減少といったさまざまな社会問題があり、これまでのような行政による一方的な整備だけでは困難になってきています。そのため、多様な市民の視点を取り入れながら「公共」のあり方をアップデートしていく必要があるとお話しされていました。

また、現在進行中のプロジェクトについてもご紹介いただきました。南池袋公園を中心とする道路空間を活用した「IKEBUKURO Living Loopプロジェクト」は、「まちをリビングのように心地よい空間にする」ことを目指しているプロジェクトです。飯石先生がこのプロジェクトを進める上で最初にしたことは、街の課題をリサーチした上で「理想の風景や暮らしを妄想し、描いてみる」ことです。コンセプトもこのプロセスの中で考案されたそうです。
また飯石先生は、いきなり完成形を決めるのではなく、実験を重ねてより良い解決策を見つけるプロセスを大切にされています。たくさん実験をすることで「風景や体験を共有する」ことができ、行政や住民を説得する材料を増やすことができます。さらに、屋台や路上のファニチャー作りなどのワークショップを街の人とともに行うことで、参加した人が「わたしたちのまちはわたしたちで創っている」という感覚を育むことができます。この感覚を街の人が共有することが公共空間をより良いものにする上で重要になるそうです。
そして、「みんなの公園プロジェクト play here」という小金井市で行っているインクルーシブな公園をつくる取り組みについてもご紹介いただきました。インクルーシブ遊具など設備の整備は進んでいる一方で、障害がある子どもを持つご両親の「公園に行きたくても行けない」という気持ちに寄り添い、真にインクルーシブな公園づくりを行っています。このプロジェクトは、たくさんの当事者の話を聞くことから始めたそうです。実際に当事者に話を聞いてみると、障害を持つ子どもが遊具の列に並べないといった悩みや、トイレ等の関連設備に関する不安、周りの目が怖いという気持ちなど、さまざまな声があったそうです。多様な当事者の問題をわかったつもりにならず、その声に「誠実に耳を傾ける」ことの重要性を強調されていました。この視点は、ストリートメディカルにおいてもとても参考になる視点だと感じました。

ワークショップ「もったいない」場所を面白い場所に
後半のワークショップでは、日常の中で「もったいない」と感じる場所に着目し、その場所をどうしたら居心地良くできるか、面白くできるかをチームごとに考えるワークショップを行いました。
受講生からは様々なアイデアがあがりました。家のシンク下や町内の掲示板、電柱といった日常の一部に着目し、掲示板を「街の〇〇自慢」としてコンテンツ化するアイデアや、電柱に編み物を巻くことで温かみを感じさせるアイデアなどがあがりました。さらに、お寺やお墓、ソーラーパネルの設置スペースなど、より公共性の高い場所を人々の交流の場やアーティストとコラボして観光名所にするというアイデアもありました。医療現場においては、病院の待合室に短時間で楽しめるショートコント動画を流すアイデアや、病院前のエントランスに療養食も提供するキッチンカーを配置するアイデアなど、病院で過ごす「時間」をより良いものにするという視点で考えられたアイデアもあがりました。

今回の講義を通じて、「公共」は誰かから与えられるものではなく、「育む」ものだと飯石先生は強調されていました。医療現場なども含め公共性の高い場所を変えようとするには、制度や設備などをを変えるというトップダウン的なアプローチをイメージしがちでしたが、現場や使う人にとことん寄り添い、多くの人を巻き込んで実験し実行するボトムアップ的なアプローチを学びました。このアプローチはストリートメディカルラボの基本理念と通ずる点があります。現在修了制作に取り組む受講生からも学びになったという声が多く寄せられました。