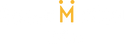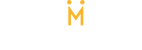2025年8月30日、第6期15回目の授業が開催されました。多摩美術大学で情報デザインやUI/UX、サービスデザイン教育を牽引、近年は「医療×デザイン」の領域でもご活躍する吉橋昭夫先生をお招きし、「サービスデザイン入門」をテーマにお話しいただきました。
講義「サービスデザインとは何か」
講義の前半では、「サービスデザイン」について、理論的な背景と具体的な方法論をお話しいただきました。サービスデザインとは「サービスを顧客の視点からとらえ、シームレスで質の高いサービス体験を創出する」ものです。その根幹にはデザイン思考があり、クリエイティブで人間中心のプロセスによって、顧客と提供者の双方にとって価値ある体験を生み出すことを目指します。
また、「製品」だけでなく「ユーザーエクスペリエンス」を提供する会社を例に挙げ、経験自体が商品価値になっている事例をご紹介いただきました。
さらに、実際に吉橋先生が手がけたサービスデザインの事例や、多摩美術大学において学生が取り組んだ事例をもとに、課題を解決する手法をご紹介いただきました。
サービスデザインは、人々の活動やプロダクト、情報、空間、プロセスなどを総合的に扱うデザイン分野であり、この考え方や手法は社会課題の解決に適用することができるとお話しされていたことが印象的でした。
ワークショップ「ペイシェント・ジャーニーを描く」
後半のワークショップでは、実際に「ペイシェント・ジャーニー」を描くワークを行いました。受講生は、自身の通院経験や職場での患者さんの受診を想定しながら、病院での体験を患者視点で書き出しました。手順の正確さではなく、患者さんの経験全体を把握することを重視して書き出すことが重要だそうです。さらに、作成したジャーニーマップの中で、患者さんが抱える悩みや問題、不便さを感じるポイント(ペインポイント)を書き出しました。このペインポイントが課題解決の手掛かりとなります。ワークショップでは作成したジャーニーマップをチームで共有し、それぞれの経験やワークを通して気づいた点を共有しました。
今回の授業を通じて、サービスデザインにおいて最も重要な点は「顧客の経験価値を描くこと」であることを学びました。自分自身の経験から得た出来事、感情、気づきを大切にしてサービスデザインを行うという点は、前回の比嘉先生の授業のフィールドワークとも通じる点がありました。タッチポイントごとに顧客の感覚や感情を丁寧に拾い上げ、全体像を設計することで、より良い体験を「具体的なかたち」として提案することができるそうです。
また、ワークショップを通し、医療現場でサービスデザインの手法を活用することで、医療現場における課題を解決する手法になりうるということを実感しました。現在受講生が取り組んでいる修了制作での課題発見において、今回のサービスデザインのアプローチが活かせるのではないかと感じました。