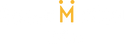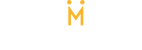2025年7月19日、第6期第11回目の授業には、第2回にお呼びした山本尚毅先生を再びお招きし、「チームビルディングワークショップ」を行いました。
ストリートメディカルラボでは、最終回に各チームが卒業制作の成果を発表します。受講生は、先日発表されたばかりのチームメンバーと共にワークショップに取り組みました。
良いプロジェクトを作るチームとは
授業の前半では、山本先生が手がけた高校生の進路選択支援ツール「ミライの選択」がどのように生まれたか、その背景やプロセスをご紹介いただきました。高校生が「なんとなく」で進路を決めてしまう現状に注目し、自分の意思を体系化して書き出し、考え、家族・教師とともに話し合いながら意思決定をできるようにサポートするツールです。山本先生は、この高校生の意思決定の構造が、「医療現場での意思決定(Shared Decision Making=SDM)」にも共通するものがあるとお話しされていました。
また、「進路選択における迷いの経験がもたらす学び」の研究を行うニューヨーク大学在学中の菊田さんとのトークセッションも行われました。菊田さん自身が高校3年生の時に「ミライの選択」を使ってどの大学に進学するのかを検討されたそうです。菊田さんは実際に学生との対話を行うそうで、自身が学生とコミュニケーションを取る際に気をつけていることなどもお話しいただきました。
山本先生は、これまで多くのプロジェクトに携わるなかで「うまくいくチームに共通しているのは、いい対話がなされていること」とお話されていたのがとても印象的でした。いい対話がなされるためには、「チームメンバーがお互いのことをよく知っている」ことが重要です。さらにプロジェクトをうまく進めるには「それぞれがどこを目指しているのかが分かっていて、その真ん中にプロジェクトがある」状態を作れることが重要だとお話しされていました。
「仕事」になるまえの「プロジェクト」の段階では、チームメンバーがどのくらい熱量を持って取り組めるかが重要になります。そのため、山本先生のおっしゃる状況がプロジェクトがうまくいく1つの条件であるということに納得しました。これから卒業制作としてプロジェクトを作っていく受講生にとっても、納得感のあるものだったのではないかと思います。
チームビルディングワークショップ
授業の後半では、「ミライの選択」を応用したワークを実施しました。受講生それぞれが「今、自分が決めたいと思っていること」や「ストリートメディカルへの参加をどう決めたか」などををテーマに自身の考えや価値観をスプレッドシート上に書き出しました。このワークを通じて、自身の価値観を可視化・再認識することができました。
また、作成したワークシートをもとに、卒業制作を行うチームに分かれ、チームごとにそれぞれの価値観を共有しました。オンライン・オフラインの受講生が混ざり合ってワークに取り組む姿は新鮮でした。
今回の授業を通し、このようなワークはプロジェクトを進める上での「相互理解」の土台づくりとしてとても重要だと感じました。ワークがあるからこそ、普段の雑談では辿り着けないそれぞれの深い部分にある価値観も共有できるのだと思います。相手を理解することはもちろん、自分を開示することの重要性も感じました。チームビルディングは、それぞれの価値観や関心、悩みを理解しながら「同じ課題や目標を共有すること」だと改めて実感しました。
いよいよ卒業制作に向けたチームでの活動が本格的にスタートします。それぞれの問いや想いを起点にしながら、どのようなプロジェクトが形づくられていくのか、今後の展開がとても楽しみです。