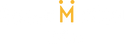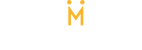2025年6月7日、第6期第6回目の授業には、クリエイティブディレクターの佐藤夏生先生にお越しいただきました。「ストリートメディカル」の生みの親でもある佐藤先生に、アイデアの定義や発想する方法についてお話しいただきました。
アイデアとは何か
授業の前半では、佐藤先生のご経歴とともに、「アイデアとは何か?」をテーマにお話しいただきました。佐藤先生は、アイデアを「それによって何かを変化させ、新しい社会の当たり前を作るもの」と定義されており、社会との新しい関係性を生み出す力があると述べられていました。
例えば、「風邪の引き始めに風邪薬を飲む」「喉が渇く前に水分を補給する」といった人々の認知を変えた広告の事例や、「熱中症」「減塩」「三密」といった新しい概念に言葉を与え人々の行動を変えた事例もご紹介いただきました。言葉の選び方や、新しい言葉を作ることもアイデアの一つであるということを学びました。
ある事象に対して新しい言葉を生み出すことで問題を可視化し、社会を変えるという考え方は、まさに「ストリートメディカル」の根幹にある考え方だと感じました。

アイデアは磨くもの
また、アイデアのヒントは社会に落ちており、それを見つけることが重要であるとお話しされていました。自分の視点だけでなく、家族や友人など他者の視点からも社会を観察することで、より多くのアイデアに出会うことができるそうです。さらに、考えたアイデアからいくつかを選び、「より良いアイデアにする方法を長期に渡って考える」プロセスが大切だとお話しされていました。また、仲間とともに脱線したり散らかしたりしながら磨く過程が重要だと強調されていました。
AIの発展により合理性が重視される現代において、「クリエイティビティ」こそが人間ならではの強みであり、数字ではなく共感によって理解を得る力がますます求められているという点も、非常に興味深かったです。

授業の最後には、「新しいドラえもんの道具」を考えるワークショップを行いました。このワークを通し、固定概念を取り払い、自由な発想で日常の中の問題からアイデアを生み出す練習を行いました。
生徒からは、「キャッカンとシュッカン(缶)」というアイデアが挙がりました。自分が主観的になりすぎている時にはキャッカンをあけ、逆に客観的になりすぎている時にはシュッカンをあけることで、思考のバランスを整えるための道具です。発想とネーミングがとてもユニークなアイデアでした。その他にも、「人の精神年齢通りに見えるメガネ」や「自分の欠点を言うと美徳に変換してくれる翻訳機」など様々なアイデアが挙がりました。
今回の授業を通じて、アイデアは天から降ってくるものではなく、日常の中にヒントがあり、日々の生活の中で地道に探し、磨き、育てていくものであることを実感しました。現在個人課題に取り組んでいる生徒の皆さんにとって、学びの多い回になったのではないかと思います。様々なユニークなアイデアが発表されることを期待したいです。