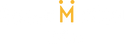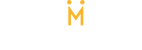2025年6月23日、第6期第7回目の授業には、デザイナーの長谷川哲士先生をお迎えしました。株式会社minnaの取り組みや長谷川先生が考えるデザインの定義、これまでに手がけた事例を通じて、「優しいデザインの作り方」についてご講義いただきました。
株式会社minnaのコンセプトとデザイン
長谷川先生は、パートナーの角田さんとともに株式会社minnaを設立し、「公私混合」をスタンスに活動されています。ネガティブな印象のある「公私混同」ではなく、日々の生活から得られる視点や人とのつながりを仕事に活かすというポジティブな意味を強調されていました。実際に日々の生活から得られる視点が仕事に生かされたり、子どもと通じた人とのつながりが新たな仕事につながるというケースも多いそうです。
また、「クライアントからの依頼が本当にその人たちのためになっているのか?」という問いを常に立てながら仕事に取り組んでいることが印象的でした。たとえば、ポスターのデザイン依頼に対しても、単に依頼されたものを作るのではなく、「そもそも何を作るべきか?」という段階からクライアントとともに考える姿勢を大切にされているそうです。「自分で診断してから病院に行く人はいない」という医療現場の比喩で説明されており、ストリートメディカルラボの受講生にとっても納得感があったようです。
デザインの作り方
講義の後半では、これまでに長谷川先生が手がけたパンフレットやロゴ、壁紙などの事例をご紹介いただきながら「優しいデザイン」について解説いただきました。細部にまで意味を込めたロゴや名刺のデザイン、依頼内容をさらに発展させて多くの人が関わることができるようにしたポスターフォーマット、さらには自身の子育て経験を活かしたデザインなど、いずれもクライアントとの丁寧な対話から生まれた温かみのあるものばかりでした。
実践ワークショップ
授業の最後には、実際の案件をもとにしたワークショップを実施しました。テーマは、長谷川先生が過去に受けた「子ども向け体験型アート施設」からの依頼をもとに、参加者自身のアイデアを考えるというものです。「入場料以外の収入源を作りたい」「子どもたちが制作したアートを持ち帰ってもらいたい」という2つのクライアントの要望を下にアイデアを考えました。
受講生からは、以下のような様々なアイデアがあがりました。
・子どもたちが作ったものをデジタル化するサービスを展開する
・親が持って帰りたくなるもの(トートバックやキーホルダーなど)に子どもが絵を描けるようにする
・夏休みの自由研究パッケージを行う、体験型施設の客層を広げる仕組みを考える
長谷川先生が実際にデザインを考えた際には、「子どもたちにはこれまで通り無我夢中に遊ばせる」「クライアントに無理をさせない中であたらな価値を生む」の2点を特に意識してデザインをされたそうです。受講生からは納得の声が上がっていました。
まとめ
今回の授業を通して、「デザインとは、単に色や形を整えることではなく、対話によってかたちになっていない想いや理想を可視化するプロセスである」ということを学びました。長谷川先生が紹介していた「ハッピーなデザインで、みんなをつなぐ」という考え方は、ストリートメディカルのコアにある考え方とも通じるところがあります。受講生からは「デザインに対する捉え方が大きく変化した」という声が寄せられました。長谷川先生のクライアントに真摯に向き合う姿勢は、デザインに馴染みのなかった受講生にとっても学びが多かったことと思います。