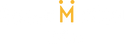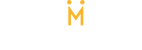2025年5月31日、第6期第5回目の授業には、フリーアナウンサーの町亞聖先生にお越しいただきました。ご自身の経験や取材をもとに、ソーシャルワークのあり方についてお話しいただきました。
すでに社会は共生している
講義の前半では、町先生が東京パラリンピックの取材を通して感じられたことをご紹介いただきました。「障がい」と一言でいっても、先天的なものから、事故や病気によって後天的に抱えるケースまで、その背景や程度は実にさまざまです。町先生は、誰もが「協働」できる社会をつくるためにご自身の活動を行っています。
また、町先生ご自身がヤングケアラーの当事者であった経験についても触れられました。「必要なタイミングで必要な支援を届けること」や、一時的な支援だけでなく継続的な「自立支援」が重要であるということをお話しいただきました。
「共生社会を目指すのではなく、すでに社会は共生しており、困難を抱える人々が社会の課題に光を当ててくれているのだ」というお話しがとても印象的でした。町先生のお話を通し、誰もが自分らしく生きられる社会を支えることが、成熟した社会の目指す在り方だということを改めて実感しました。

誰かの困りごとは社会のニーズである
また、企業がガン撲滅のために行ったキャンペーン、新しい取り組みを行う高齢者住宅など、誰かの困りごとを社会のニーズと捉え、行政だけでなく民間からも社会を変えるムーブメントを起こしている事例をご紹介いただきました。
行政が必要な制度を用意していても、それが本当にに必要な人へ届けるためには、周囲の人が「気づき」「繋がり」「行動する」ことが重要だというお話しをされていました。町先生は、ソーシャルワーカーは決して特別な資格ではなく、「誰もがソーシャルワーカーになれる」ということを強調されていました。
困っている人を見かけたら自然に助けてあげられる人でありたいと感じるとともに、何かがあった時に「きっと誰かが助けてくれる」と思える社会への信頼を醸成することの大切さも感じました。
ワークショップ「身の回りのジェンダーギャップを考える」
授業の後半には、生徒のみなさんが日々感じるジェンダーギャップについてグループで話し合うワークショップを行いました。生徒からは以下のような様々な案が挙がりました。
制度や社会構造に起因するジェンダーギャップ:
・男性の方が育児休暇がとりにくい
・女性の管理職の比率が少ない
・男性の方が転勤や出張で遠方に行きやすい
文化や社会から期待されるジェンダーロールに起因するギャップ:
・授乳室やおむつ交換台が女性トイレにしか設置されていない
・大きな買い物(家電・住宅など)の説明が男性に向けてなされることが多い
企業のサービスや製品におけるジェンダーギャップ:
・多くの製品が男性の平均体型を基準に設計されている

自分自身の当たり前を疑い、他者の声に耳を傾ける
今回の授業を通し、日々の生活の中で無意識に持つバイアスの多さに気づかされました。そのバイアスに気づくためには、誰もが自身の体験やそれを通して感じたことを共有し、社会がそれに耳を傾ける必要があります。しかし、特に障がいのある方にとっては、声を上げること自体が「わがままだ」と受け取られるケースも多く、まだまだ社会の側が声を聞き入れる準備ができていないと感じます。自分自身の当たり前を疑い、誰かの声に耳を傾けることの重要性を感じました。