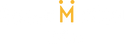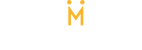2025年5月11日、第6期2回目の授業が開催されました。今回のテーマは、「想像とデザイン」。日本総合研究所フューチャーデザイナーの山本尚毅先生にお越しいただきました。
講義「想像とデザイン」
山本先生は、今回のタイトルでもある「想像とデザイン」をテーマに幅広いお仕事をされています。

講義では、参加観察や、ビジネスエスノグラフィーなどの文化人類学を手法についてご紹介しました。また、ポジティブ・デビアンの研究や、ナッジ(ナッジ)の活用など、人の行動を変えるためのデザイン的アプローチについても解説いただきました。
また、1990年代以降も使われてきた「VUCA(不安定で予測困難な社会を表す概念)」に代わり、2020年前後から「BANI」という言葉が現れているそうです。災害や気候変動、社会分断により予測不可能で脆弱な世界情勢が深刻化したことが背景の言葉にあります。VUCAが脆弱な仕組みや社会特異を表した客観的な言葉であるのに対して、BANIは、社会構造やシステムを分析するだけでなく、人間の感情や主観に注目し、変化に対する「内面の回復力」や「理解力」といったレジリエンスをどう育む考察視点です。
ワークショップ「儀式」と「通過儀礼」
ワークショップでは、「儀式(Ritual)」と「通過儀礼(Initiation)」をテーマに、個人ワークとグループワークを行いました。
儀式には文化人類学の学問で研究されるような民族に伝わる儀式から、日常の中でライフハックや自己啓発のコンテキストで捉えられるものまでさまざまなものがあります。
また近年は、儀式を科学的に研究した書籍の出版もあり、儀式をデザインすることへの関心が高まることが予想されるそうです。
①個人ワーク「あなたに儀式はある?習慣と儀式の違いは?」
まず、自分の生活の中にある「儀式」について考え、さらに「習慣」との違いについて意見を出し合いました。「儀式は意識的に行うもので、しなくても困らない」「習慣は無意識で、生活に欠かせない」などの意見が挙がりました。
山本先生が紹介された書籍『RITUAL(リチュアル): 人類を幸福に導く「最古の科学」』では、習慣は因果関係が明確で合理的である一方、儀式は因果関係が不明瞭で不合理なものとされています。不合理さも受け入れる時代への変化が背景にあるのではないかとお話されていました。
②グループワーク「名刺の面接をリデザインするサービスをどう使うか?」
2つ目のワークでは、ビジネスの慣習として定着している「名刺交換」という儀式の場で、デジタル名刺サービスを実際に使うにはどうすればよいかをグループで考えました。答えのない問いに各チームは苦戦しながらも、「オンライン名刺を使うことを事前に共有することで文化をつくる」「デジタル名刺を話しのネタにし、名刺交換に違和感を感じている人の共感を得る」「複数の名刺をシーンに応じて使い分ける」など、多様なアイデアが出されました。
今回の授業を通じて、文化人類学的視点から行動変容を捉える方法や、BANIという新たな概念の意義を学ぶことができました。社会の構造や制度を分析するだけでなく、そこに生きる「人」の感情や不安に寄り添う視点の大切さを実感しました。これは、ストリートメディカルラボが目指す、病気だけでなく、人のウェルビーイング全体を考えられる人材を育てるというテーマに通じると感じました。不確実なことが多い世の中において、今後より必要になってくる視点だと実感しました。
また、ある生徒のレポートには「今回のグループワークでは、メンバーそれぞれの多様な意見が飛び交い、ストリートメディカルの特徴である多様性を実感できた」との感想がありました。今後の授業でも、普段の生活では出会えないような価値観や背景を持つ講師・生徒と共に学び合い、新たなアイデアを生み出すプロセスを体験してほしいと思います。