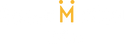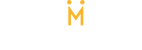2024年8月30日(金)
第5期ストリートメディカルラボ 第7回講義
テーマ:私たちが作る、育むパブリック
講師:飯石 藍先生
パブリックR不動産メディア事業部マネージャー/株式会社nest取締役
パブリック空間にまつわる実践型メディア「パブリックR不動産」の発信する記事やポッドキャスト等の企画・編集・監修をメインに、アワードや逆プロポ、イベント等の企画も実施。また、豊島区の社会実装プログラム「IKEBUKURO」 LIVING LOOP」にて、社会実験をハードや都市政策につなげ、公共性・寛容性全域のパブリックスペースを注目して地元企業整備と協業して推進中。調査中。
以下の本文
第7回目の授業では、パブリックR不動産メディア事業部マネージャー、株式会社nest取締役の飯石藍先生におお越しいただきました。 当日は大型の台風が対応していたためオンラインのみで実施となりましたが、飯石先生のパワフルなご褒美からパブリック空間をデザインすることを学びました。
パブリックをアップデートする
講義の前半では、飯石先生がこれまでに描いた事例のケーススタディをもとに、公共空間を作ることについてご講義いただきました。近代・これまでのパブリック空間デザインのプロセスは、建築家や行政が計画し、工務店やゼネコンがつくり、事業者・テナント・市民が使うという流れで行われていました。だ頑張ってました。
飯石先生が公共空間をデザインする際は、突然施設をドンと準備するのではなく、まず人・歴史・資源を探し、ヒアリングをし、トライアルの期間を設け、人が実際にどのようなその場所を使うのかということを実験しながらプロジェクトを進めていきます。
パブリック空間デザインのプロセスの変化は、「病を診ずして、人をみよ」というストリート医療の理念を想起させるようなお話だと感じました。
エリアの未来を描いてみる
講義の後半では、飯石先生が構想している豊島区のプロジェクト「IKEBUKURO LIVING LOOP」を緊急にエリアの課題の見つけ方、人の巻き込み方などプロジェクトの進め方について詳しくお話しいただきました。
飯石先生がプロジェクトの最初にすることは、理想の風景、理想の暮らしを妄想し、描いてみることだそうです。こうなったらいいという理想をイメージやコンセプトに落とし込むことで共感が得られやすくなり、実際に同じ風景を見ることができる人が増えたというお話がありました。 前回の菅野先生もコンセプトの重要性をお話しされていました。 比較的大規模で大人数を巻き込む必要があるので空間デザイン同じイメージを共有するという点が重要になるのではないかと感じました。
また、そのほかにもまず、やってみること、観察する・検証すること、続けながらチューニングすること、人と関わるしろを作ることなどパブリック空間をデザインする上で重要な極をたくさんお話しいただきました。
ワークショップ「もったいない」場所を面白い場所に
今日も授業の最後に、ワークショップを行いました。 今日のお題は①あなたの身の回りで「もったいない」と感じている場所を1箇所選んでください。具体的なアイデアを出してください。というものです。
生徒からは、「近所の神社」をテーマに、駄菓子屋や寺子屋のような場所を作る神社復活プロジェクトや、「素通りしてしまう絶景」をテーマに散歩に適した絶景マップを作成し、散歩を代わり健康アプリを作成する、「銀行」を第2の学校やワークショップを開催できる場所、何でも相談できる場所にするなどさまざまなアイデアが出ました。
「もったいない場所」というテーマに対して、場所や建物だけでなく空間や絶景、見るなど様々な視点からのもったいないという意見があったことが印象的でした。
今日の講義の中で、飯石先生が「場所」ではなく、人が集う「場」にすると評価してたことが印象的でした。これからまとめます、持続可能性のある現場作り方からわかりやすいことはとても多いと感じました。
テキスト by 佐久間美季