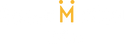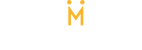ストリートメディカルラボ第5期修了発表会である「Street Medical Talks 2024」が2024年12月22日、日本橋ライフサイエンスビルにて開催されました。
当イベントは、受講生による修了発表を行うプレゼンテーションイベントです。 ストリートメディカルラボ学長の武部貴則先生、フリーアナウンサーの町亞星先生、一般社団法人ステラサイエンス財団ストラテジックデザイナーのショーン・マッケルベイ先生、日本総合研究所スペシャリストの山本尚毅先生をメンターとしてお迎えしました。
ストリートメディカルを目指すもの
イベントは、武部先生の講義「ストリート医療を目指すもの」から始まりました。武部先生がストリート医療を目指す未来と実現の可能性、アプローチについてお話しました。

超高齢社会・超コミュニケーション社会である現代において、武部先生は自己実現の障害が「命を忘れかすもの」から「生活を霧かすもの」へ変化していると指摘しています。
武部先生承YCU-CDCでは、暮らすだけで誰もが自己実現に定る都市「イネーブリング・シティ(Enabling City)」の実現のための努力を行っています。ではなく、幸福も同時に追求するという点を武部先生は、この新しいアプローチを「イネーブリング」は、ただ健康問題に言うのではなく、幸福具体的には、ポジティブな感情(嬉しい・面白い・楽しい・感動)、魅力的なメント(いきいきする、没頭)) 、人間関係(他人とのよい関係)、意味(意味・意味)、達成(達成感)の5つからなるHappiness Factor(PERMAModel)を街の中に増やすことを目指しています。
また、武部先生は講演の終盤に「健康、幸福に関する研究論文はあるが、健康、幸福の両方を研究している論文(幸福をトリガーに健康になる)の数はほとんどありません。」と話しました。医療現場における課題や社会における健康課題ドリブンに解決するためには、医学領域を超えた多分野の協力が必要です。そして、それはストリートメディカルラボのカリキュラムにも反映されています。

第5期生徒による修了発表
プレミアムトイレサービス「スマートポッティ」



最初のチーム「トイレ」ハンターズ」の発表は、過敏性腸症候群(IBS)の患者さんの急なトイレ駆けニーズに緊急トイレサブスクリプションサービスの提案です。 IBSは、一般的な検査では原因が思いつかないもの、腹痛や下痢、便秘などの症状が慢性的に持続する病気です。 このサービスの利用者は、専用のアプリからトイレを飲食店や商業、オフィスビルなどの施設のきれいなトイレを予約し、待ちずに確実にこの病気のネガティブなイメージを新たに、サービス利用者の正しい習慣の改善・生活の質を向上させることを目指したサービスです。
またショーン先生からは、トイレについて話すことに対して感情的な態度をような優しくスタイリッシュなビジュアルを評価するコメントが、さらに、日本よりも海外においてもトイレのニーズが高いことからグローバル展開の可能性などについて提案がありました。

様々なにおいを嗅ぎ分け、嗅覚で遊ぶ新感覚エンタメ「NIOI MATRIX」



チーム「ヘルスニッファーズ」の発表は、年齢とともに盛り上がる「嗅覚」に注目し、楽しい脱出ゲーム、ラボ、ショップ、カフェなど併設されたエンターテイメント施設の提案です。 の注目になると言われています機能障害を考慮してリスクが高まることにも注意ず、日常生活で気づきにくい、健康診断でも考えられていない点に目をつけたアイデアです。を増やすこと、医療領域に関しては発展途上の医療分野の探究や医療技術の普及などの効果を目指しています。

山本先生からは、においから想起される記憶に着目し、一人一人の記憶に合わせて施設カスタマイズされた香りのサービスなどの提案がありがとうございました。 嗅覚領域の可能性ふれ、着眼点を評価するコメントが寄せられました。
企画の詳細はこちらから
誰かと話してさみしも水に流れそう 「つながるトイレ」



「心のトイレ推進委員会」チームの提案は、実際のトイレの個室空間を利用し、誰かと話すことによって孤独感を癒すコミュニケーションサービスです。20〜30日間のうち、孤独感を感じる人が半数以上、さらに孤独を感じたときに相談できていない人が現状に着目したアイデアですこのサービスの利用者は、別の場所の「つながるトイレ」そこにいるどこかの誰かと匿名で5分間話すことができます。トイレ、泣くトイレなど、さまざまなケアにつながる場所やモノを「心のトイレ」とするプロジェクトです。
武部先生からは、トイレの利用時間とメンタルヘルス関連の事例が紹介され、トイレのストレスコーピングとしてのさまざまな利用目的の可能性についてコメントがありました。
企画の詳細はこちら

更年期の新しい捉え方「第二思春期」



ストリートメディカルラボの運営スタッフで結成された「チームめのぽ」は、更年期のネガティブなイメージを改め、理解や治療を促進させるキャンペーンを提案しました。のカゴや電車内のポスターで取り付けます。思春期もホルモンのゆらぎによって起こる自然な変化ということを理解してもらって、婦人科の受講、周囲の理解・サポートを続けるアイデアです。これらの課題の解決を目指します。
メンターの先生方からは、更年期の当事者に対してだけでなく、その周囲の家族、職場、社会などややゆっくりとした形を評価する声が上がりました。重要な点についてコメントをいただきました。
企画の詳細はこちら

不健康マッチング 〜健康になりたいきっかけをご用意しました〜



チーム「みちばたmeet」の発表では、不健康マッチングを繋ぐことで、楽しみながら健康マッチングになるシステムが提案されました。 健康診断で有初見と判定された人を対象に、「不健康マッチング」のお知らせが健康保険組合から届く仕組みです。料理コース、ワインコース、街歩きコースなど様々なコースが用意されており、好まれコミュニティあり、サービスなど健康習慣を作るきっかけを提供し、健康習慣の持続や、組織全体の健康レベルの向上を目指します。企業の保健師として働くメンバーの、健康診断の結果がよくない人が生活習慣を改善するきっかけをなかなか見つけられないという課題感から考えたアイデアです。
山本先生からは、前述の武部先生のアプローチでいう健康アプローチになりがちなテーマに関して、幸福主導のアプローチになっている点を評価するコメントがありました。
企画の詳細はこちら

「FUKANZEN」やさしさわかちあいプロジェクト 〜寄付で、自分も人もハッピーに〜



「ヤサシイセカイ」チームは、寄付を通してやさしさをわかちあえる病院の仕組みを提案しました。
医療費の支払いの際に少額の寄付を選ぶシステムや、カード決済に合わせてテープカットの演出が行われる設備など、思わず寄付をしたような座布団を作ります。
ショーン先生、町先生からは、寄付したお金で実際に誰を支援したのかを見える化する必要性についての指摘がありました。目的が明確な方から支援を受けやすい、支援した相手からのメッセージなどがあると支援するモチベーションになるなどの意見がありました。
企画の詳細はこちら

スティグマに悩む患者さんの心を守る「こころまもり」



このテーマの背景には、医師による正しい説明が不足しているために、ウイルス性肝炎の患者さん自身が自分の病気について十分な理解ができていない課題がこのプロダクト「こころまもり」は医師が患者さんに説明するために使うパンフレットと、それを入れて持ち運べるお守り型の絆創薬ケースです。
メンターの先生方からは、一般的なパンフレットの形にはならず、携帯できる形のプロダクトについて評価がありました。
企画の詳細はこちら

学長賞発表
メンター陣による紛糾した議論の結果、第5期ストリートメディカルラボ修了発表の学長賞は「不健康マッチング 〜健康になりたいきっかけをご準備しました〜」となりました。実現可能性の高さ、新規性の高く、新たな動きを起こす可能性の高さという点で評価しました。

修了に寄せて
今日の話、2024年7月から年間開半講されたストリートメディカルラボ第5期が修了しました。各チームとも、授業で学んだことを最大限に吸収し、ギリギリまで何回もブラッシュアップを重ねたとても良い発表だと感じました。
各チームのアイデアの今後の展開がとても楽しみです。
武部先生からは、ストリート医療で出会った人や場所、環境との関係性を今後も継続し、ストリート医療な活動が増えて欲しいと総評がありました。当ラボで学んだことをそれぞれのフィールドに持ち帰り、多くの生徒が活躍することを期待したいです。
メンターの皆様からも励ましと期待の言葉がたくさん寄せられました。
第5期はこちらで完了しましたが、次はこの企画の実現に向けてさらに頑張っていきます。
皆さん、半年間本当にお疲れ様でした。

テキスト by 佐久間美季